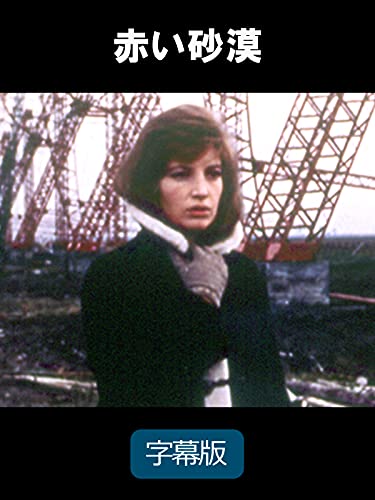★★★
工場地帯。ジュリアナ(モニカ・ヴィッティ)には夫ウーゴ(カルロ・キオネッティ)や息子バレリオがいたが、昔の交通事故が原因で精神的に病んでいる。そのせいでしばしば奇行に走っていた。彼女は夫の知人コラド(リチャード・ハリス)を紹介され、しばらく一緒に話し合う。その後、港近くの小屋に入って男女6人で馬鹿騒ぎする。ところが、ジュリアナはここでも奇行に走るのだった。やがて彼女はコラドと不倫する。
ミケランジェロ・アントニオーニが描いているのは愛の不毛ではなく、資本主義の不毛のような気がした。『太陽はひとりぼっち』には資本主義の心臓部である証券取引所が出てくるし、本作には資本主義を支える工場地帯が出てくる。どちらも不快に感じる描き方だ。証券取引所も工場地帯もとにかくうるさい。落ち着いて話していられないほどである。さらに本作の場合、喧騒に加えて工場の煙突から煙という毒物を吐き出している。工場から立ち上る煙は経済成長の証だ。こういった禍々しい光景がジュリアナの病とリンクしている。まるで荒涼とした風景が彼女の心象を表しているかのように。産業革命によって工業化が進み、同時に人々が精神的に病むようになった。資本主義社会での生活は一見すると華やかだが、人間を本来の生から疎外する。人生を生産と再生産というシステマティックな行為に還元させる。我々はその営みに耐えられない。ジュリアナの病にはそういった資本主義の病理が仮託されているように見える。
劇中でジュリアナは様々な奇行に走っている。もっとも印象的だったのが、労働者から食べかけのパンを買い取って頬張るシーンだ。別に飢えているわけでもないし、金がないわけでもない。売店だって近くにある。にもかかわらず、食べかけのパンを買い取っている。見知らぬおっさんの歯型と唾液がついたパンなんて嫌悪感しかないだろう。それを敢えて食べるのだから不気味である。これに比べたらいかにも病んでますといった感じのぐったりしたシーンは迫力がないし、自動車に乗って埠頭から海に飛び込もうとするシーンもハッタリにしか見えない。労働者から食べかけのパンを買い取って頬張る。これ以上に説得力のある奇行は見当たらなかった。
ヴィジュアル的にすごかったのが港近くにある小屋である。中は板壁で区切られているのだが、周囲を赤く塗られた居室がすごかった。その狭い部屋に男女6人がひしめき合っている。この絵面のインパクトといったら言葉では言い表せない。外界から隔絶された赤い部屋。極めて小さい、内輪だけの楽しい空間。享楽的な宴の間といった風情である。僕はこれを見て小学校時代に遊んだ秘密基地を思い出した。空き地の外れにある小さな物置小屋。そこに友達数人で侵入してよく遊んだものである。大人になってもそういう遊びができるのはなかなか稀有かもしれない。
ジュリアナとコラドはいかにも俳優といった佇まいで、突っ立って話しているだけで様になっている。あまりに決まっているのでちょっと不自然に感じた。ただ、芸術として見るなら目の保養になる決まり方である。映画というのは自然か不自然かよりも、審美的な美しさのほうが重要だ。ジュリアナ役のモニカ・ヴィッティ、コラド役のリチャード・ハリス。どちらも画面を彩る名優である。一方、この2人に比べるとウーゴ役のカルロ・キオネッティにはオーラがない。しかし、それも含めて絶妙な配役だろう。