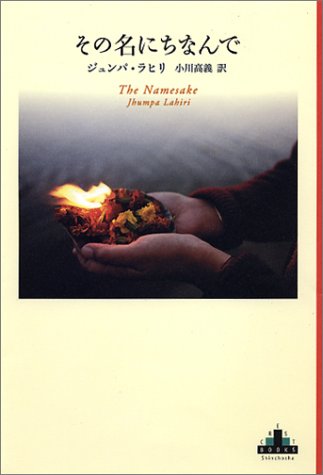★★★★
ゴーゴリと名付けられたインド系移民2世の半生。父が息子にその名をつけたのは、若い頃に列車事故に遭った際、その作家の本を持っていたことで救われたからだった。ゴーゴリも少年時代はその名前を受け入れていたが、反抗期になってから違和感をおぼえ、大学進学をきっかけに改名する。自由になったゴーゴリは人並みに恋愛を重ねていくのだった。
「父さんは、このゴーゴリとは縁が深いように感じてるんだ。ほかの作家よりも、ずっと深い。なぜかわかるか?」
「作品が好きだから」
「それもそうだが、それだけじゃない。故郷を離れて暮らすようになった人なんだ。父さんみたいに」
ゴーゴリはうなずく。「そうだね」(p.96)
基本的には文化的背景の異なる親世代とのすれ違いを描いている。移民2世のゴーゴリは、1世とは違って母国への想いはないし、3世とは違って自身のルーツ探しもしない。アメリカ生まれのゴーゴリにとって、両親が大切にしているベンガル人の縁はいささか窮屈なもので、そこに帰属意識はなかった。どちらかというと、彼のアイデンティティは生まれ育ったアメリカに根ざしている。高い教育を受けた彼は、そこらの白人と同じくエリートコースを歩んでいくのだった。
自我が芽生えたゴーゴリにとって、喉に刺さった魚の小骨になっているのが、親からつけられた自分の名前だ。この時点で彼は名付けられた本当の理由を知らず、ロシアの作家にちなんでいることしか分かってない。ニコライ・ゴーゴリ。作家としては天才だった反面、精神が不安定で薄幸の生涯を送った。インド系の名前にしては風変わりだし、そもそも元のロシア語では名字だった。つまり、現代で言えばDQNネームというやつである。抱美弟(だびで)とか、魔離鳴(まりあ)とか、その類。改名したくなる気持ちも分からないでもない。親世代とのすれ違いをもっともよく表しているのがこの名前で、父親から本当の由来を聞かされるまでその問題がついて回っている。
中盤でゴーゴリが自分の名前の真相を知るところが本作における感動のピークだろう。その後も人生は続いているのだけど、父親の死を除けばほとんど余滴と言っても差し支えない。そして、終盤で意外なのがゴーゴリの結婚相手で、同じベンガル人の女性と結婚するのはなかなか反動的だと思った。というのも、僕はてっきり白人女性と結婚して、名実共にアメリカ人と同化するものだと思っていたのだ。しかも、そのベンガル人の女性は、結婚後に不倫をするのだから一筋縄ではいかない。ベンガル人との結婚が回帰的な行為だとすれば、相手が不倫をするのは極めてアメリカ的な行為だと言えよう。この辺、著者は明確な図式化を拒んでいるような感じがした。
それにしても、移民文学って僕なんか足元にも及ばないエリート層が題材になることが多い。本作も親世代からして既にエリートだった。物語としては面白いと思いつつも、いまいち感情移入できないのは、僕に僻み根性があるからかもしれない。もっとどうしようもない負け組の物語が読みたいなあ、と思ってしまう。格差社会のどん底にいる人の物語。そういうのは映画で観るしかないのだろうか。