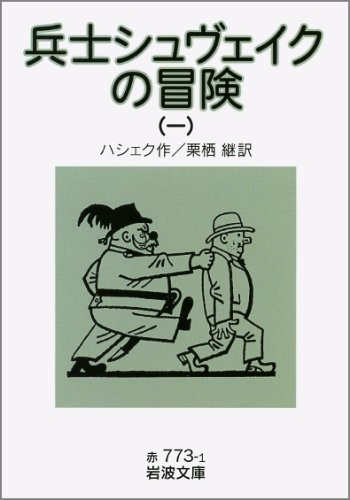★★★
1914年。フェルジナント大公がサラエヴォでセルビア人に暗殺された。ボヘミア王国(チェコ)のプラハで犬の売買を生業にしているシュヴェイクは、何年か前に軍の医務委員会から白痴の裁定を下され、兵役を解かれている。その彼が紆余曲折を経て世界大戦に参戦することに。ルカーシ中尉の従卒になって前線へ向かう。
「看守長を見ていると、戦争がいかに人間を野性にかえらせるか、いちばんよくわかるね」と、一年志願兵は考察をつづけるのだった。「うちの看守長だって、軍務につくまでは、きっと一かどの理想を持った青年だったろうと思うな。おそらく彼はだれにもやさしくて感受性の強いブロンドの天使のような存在であり、村祭の喧嘩で弱者を助けるためにはステッキをふるうこともあえて辞さなかったろうよ。みなに敬愛されたとしても、不思議ではないさ。ところが今日では……いやはや、おれはあいつの横っ面をひとつはり飛ばし、あいつのドタマをひっつかんでこの木のベッドにかちんと当て、あいつをさかさまに糞壺にたたきこんでやりたくてうずうずしているんだからな。いやまったく、これも軍隊生活というものが、いかに人間の思考を完全に野性化させるかの、何よりの証拠なんだ」(vol.2 p.139)
全4巻。
戦争小説はシリアスに書く場合とサティリカルに書く場合の2種類に分けられるが、第一次世界大戦を題材にした本作は後者である。登場人物の愚行にスポットを当てているところや、話がしばしば脱線するところなど、本作は『ドン・キホーテ』【Amazon】に近い。主人公のシュヴェイクは従卒なので、差詰めサンチョ・パンサのポジションだろう*1。シュヴェイクは上官たちから白痴や馬鹿扱いされているものの、実際はそこまで愚鈍ではない。彼は既存の価値観を揺さぶるトリックスターであり、弁舌で相手を煙に巻くのが上手い喜劇的人物である。そんなシュヴェイクはやっていることもけっこう抜け目ない。ルカーシ中尉から犬の調達を依頼された際には大佐の犬を盗んで渡しているし、さらに別の人物にはありふれた雑種犬を純血種のスピッツだと言って掴ませている。シュヴェイクは基本的にとぼけた味わいのおっさんだが、窮地から脱する能力はなかなか高く、見ようによっては頭がいいと言えるかもしれない。彼がその天然ぶりで問題を起こしてルカーシ中尉を困らせるところは傑作だ。中尉はちょくちょくシュヴェイクの巻き添えを食っている。
風刺を目的にした小説だけあって、社会の歪みをアイロニカルに捉えているところが印象に残った。たとえば、従軍司祭が兵士を相手に戦意を高揚させるような演説をしている場面では、宗教ってろくでもねーなーって思ったし、神の名において殺人を煽動するところは、およそ近代とは思えない野蛮さだと思った。現代のキリスト教徒はイスラム教徒をテロリストだと断罪しているが、歴史的に見たらキリスト教徒のほうが遥かに悪質だろう。彼らのやっていることはイスラム教のジハードと何が違うのか。他にも、兵士が便所掃除を拒否しただけで反乱罪に問われたり、秘密警察が無実の人間を無理やり政治犯にでっち上げたり、戦時中の社会はとにかく不条理なことばかりである。こういう天地が逆さまになったような状況は、現代だとブラック企業でしか体験できないだろう。特に軍隊で上官とやりとりする状況は、会社でパワハラ上司とやりとりする状況ともろに被る。ブラック企業に勤めている人は、本作を読んで身につまされること請け合いだ。
古典を読む醍醐味は、現代人との共通点や相違点を探るところにあるが、僕は本作を読んで、いつの時代も人間は愚かだと思った。序盤でシュヴェイクが精神病院にぶち込まれた際、「あそこの生活は、まずこの世の天国といった感じでしたね」と言って、その自由さを称揚するところは逆説的で、狂っているのは人の自由を縛るこの世の中だということを示している。とかくに人の世は住みにくい。
*1:ただし、ドン・キホーテに該当する人物はいない。