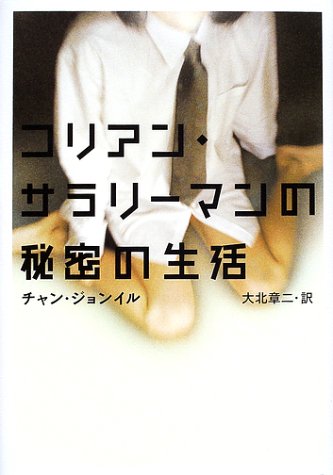★★★★
大学生の「ぼく」は余暇に小説を書いていた。その主人公トレリスは罪と報いについての小説を構想しており、登場人物を何人か創造して自分と同じホテルに住まわせている。トレリスの創造した人物たちは、彼のコントロールを離れ、トレリスに一服盛って昏睡状態にしてしまう。その後、トレリスの私生児が復讐目的でトレリスについての小説を書くのだった。
小説と戯曲はともに楽しき知的実践である。小説は幻想の外的投影物に欠ける点において戯曲に劣るが、しばしば姑息な手段で読者をペテンにかけては架空の作中人物の運命に人ごとならぬ関心を抱かしめる。戯曲は公共建造物において多数観客の健全なる観賞に供せられ、小説は密室における個人のひそやかな楽しみの具である。節度に欠ける作者の手にかかるとき、小説は独裁専制的なものになりうる。あえて言うならば、申し分なき小説は紛うかたなき紛い物でなければならず、読者は随意にほどほどの信頼をそれに寄せればよいのである。(p.34)
ナンセンスなメタフィクションで面白かった。『第三の警官』の惹句に「アイルランド的奇想」というフレーズがあって、当時それを読んだときはいまいちピンとこなかったものの、本作はまさしくアイルランド的奇想が横溢した小説である。というのも、作中にフィン・マックールという古代アイルランドの英雄が出てくる*1。さらに、スウィーニー王の狂気にまつわる物語を詩を交えて語るところや、プーカという魔術的人物の前にグッド・フェアリなる妖精が現れるところなど、あまりアイルランドに詳しくなくてもこれはアイルランドっぽいと感じる。思えば、『第三の警官』は自転車が中心の世界観だったから、「これがアイルランド?」と首を傾げたのだった。本作は語り手が文学におけるアイルランドおよびアメリカ作家の優越性を友人と語り合っていたのが印象的だ。イギリス作家を腐しているところがポイントで、当時のアイルランド人がイギリスのことを嫌っていたのが窺える。
全体としては人を食ったような話で、毒にも薬にもならないただただ純粋な創作物であるところが好ましい。上の引用の通り、「申し分なき小説は紛うかたなき紛い物」なのだ。まさに小説のための小説といった感じである。本作より面白いメタフィクションはたくさんある。しかし、この時代にこういう小説を書いたことはとても貴重だと思う。
ところで、西洋文学って何かと裁判のシーンを描くことが多いような気がする。有名な古典だと、『ヴェニスの商人』【Amazon】や『カラマーゾフの兄弟』【Amazon】。最近読んだ本だと、『罪人を召し出せ』や『インドへの道』。こう書いたからには当然本作にも裁判シーンが出てくるのだが、その様子は例によってナンセンスでふざけた代物だった。やはり裁判は西洋文明を支える屋台骨なのだろう。
*1:人気スマホゲームFate/Grand Orderにも出てくるようだ。