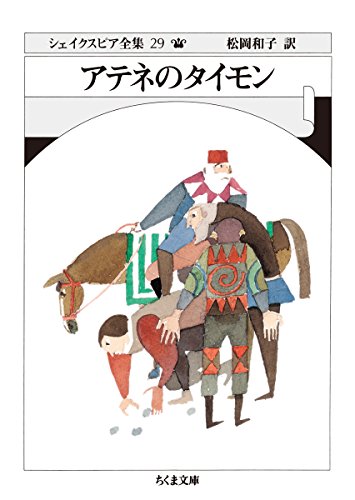★★★
盧溝橋事件によって戦争が勃発、北平が日本軍に占領される。教師の祁端宣は四世代同居の「四世同堂」の生活を送っていたが、弟の端全が城外に脱出して抗日戦に身を投じたことで、己の身の振り方について葛藤する。一方、詩人の銭黙吟は日本の憲兵に捕まって手酷い拷問を受けた。そんななか、冠暁荷、藍東陽、祁端豊は日本人に取り入って漢奸となり、冠の妻であるカラス瓜は売春婦の元締めになる。
「君はこわがらなくていい、わしは詩人で、腕力は使えない! わしが来たのは、君に会うためでもあり、君にわしを見せたいからでもある。わしはまだ死なない! 日本人は人を打つのがとてもうまい。が、彼らはわしの身体をこわし、わしの骨を折っても、心を打ちなおすことは出来なかった! わしの心は永遠に中国人の心だ! 君は? わしは君にききたい、君の心はどの国のかね? どうか答えてくれ!」(上 p.197)
長かった。2段組みで1300頁もある。抗日戦争が題材ということで、戦場での日々が描かれるのかと思ったら、舞台は小羊圏という横丁に終始していて、日本に占領されていることを除けばいつもの中国文学だった。横丁に住む庶民の生活、彼らの人間関係に焦点を当てている。占領下での身の処し方がそれぞれ違っていて、大多数の人は日本人を憎んでその禄を食まないようにしていた。その一方、少数の漢奸が日本人に取り入って富と地位を手に入れようとしている。たくましいというか何というか、さすがに「勝ち馬に乗れ」がモットーの僕でもこれにはどん引き。もし自分の住んでいる地域が外国に占領されたらどうすべきか、ちょっと考え込んでしまった。命が惜しいから進んで抵抗することはないだろうし、かと言って協力するのも癪だから相手に取り入るようなことはしたくない。静かに怒りの炎を燃やしながら災厄が去るのを待つことになるだろう。小羊圏の人たちも概ねそんな感じで生活しており、漢奸たちとの摩擦がドラマを面白くしている。
先の戦争については、原爆の投下や本土の空襲によって日本人は自分たちを被害者と位置づけがちだが、実はアジアに対して加害者だったことは明白なので、そのことは忘れてはいけないと思った。ここ数年、日本では「ニッポンすごい!」という軽薄なテレビ番組が流行しており、グローバル化によって自信を無くした負け犬たちの熱狂的な支持を受けている。そういう人たちにとって本作はいい解毒剤になるだろう。日本人が中国でどれだけ非道なことをし、また現地の人たちからどういう目で見られていたのか。本作はあくまで文学であって記録ではないとはいえ、僕にとっては日本を見つめ直すいい機会になった。自分たちに都合の悪い過去を切断して「ニッポンすごい!」と悦に入るのは、さすがに馬鹿っぽいと言わざるを得ない。
本作は庶民の生活を描いたいつもの中国文学ではあるが、『進撃の巨人』みたいに役目を終えたキャラを容赦なく殺していくので、その辺はやっぱり戦時下が舞台なのだと思った。漢奸たちの栄華も日本人次第なところがあって、いくら特権を得て我が世の春を謳歌しても、財産を没収されたり投獄されたりして一瞬のうちにすべてを失ってしまう。こうなると、どう身を処すのが正解なのか分からなくなってくる。それと、支配された側の命は羽毛のように軽い。ある人物は無実であるにもかかわらず、日本人のメンツのために拷問を受けて首を斬られてしまう。また、ある2人組はお上から支給された粗末な食べ物で腹を壊して病院に行くも、日本兵に郊外まで連れて行かれて生き埋めにされてしまう。外国に支配されるとはこういうことなのだとぞっとした。