★★★★★
長年の間公務員をしていたウンベルト(カロル・バッティスティ)は、愛犬のフランクとアパートで年金暮らしをしていた。ところが、彼は年金が足りなくて家賃を滞納しており、大家(リナ・ジェンナーリ)から追い出されようとしている。ウンベルトは若い女中(マリア・ピア・カジリオ)と気軽に話をする仲だったが、彼女は父親が誰か分からない子供を妊娠していた。喉を痛めていたウンベルトは、女中に犬を預けて慈善病院に入院する。
貧困を描いた映画であると同時に、終活をどうすべきか問題も扱っていて、少子高齢化に直面している我々にとっても他人事ではないと思った。
ウンベルトは妻も子供もいない「おひとり様」で、そこは世間から見れば少数派なのだけど、社会人としては長年公務員を務めていた「普通の人」である。そんな彼でさえ、貧困に陥ってしまうのだから救われない。貧困とは個人の能力の問題ではなく、景気や政策といった社会の構造的な問題である。そのことは日本でも「失われた20年」によって明らかになった。不景気だったら雇用は失われるし、少子化が進めば貰える年金の額も目減りする。また、万が一にも戦争が起きたら一億総どん詰まりになるだろう。いくら人並みの能力を持っていても、社会構造の変化による影響は避けられない。特に少子高齢化の日本ではもはや勝ち逃げすることは難しいわけで、誰もがウンベルトになる可能性を秘めている。
ウンベルトは家賃を払うべく、時計や本を売って金を得ている。しかし、それでも滞納分を返済するには足りない。切羽詰まった彼は、街頭で物乞いを見て自分もやってみようかと葛藤する。街頭に立っておずおずと手のひらを差し出すも、いざ貰う段になったら手の甲を向けてやり過ごす。また、犬に帽子を咥えさせてお捻りを貰おうとするも、それは結局失敗する。彼は物乞いをするにはプライドが高すぎたのだ。一連のシーンは尊厳と実益の間に揺れる複雑な感情が活写されていて、実に人間臭いと思った。
ウンベルトにとって愛犬のフランクは家族みたいなもので、最初から最後まで犬のことを気にかけている。行方不明になったら慌てて保健所まで探しに行くし、自殺を決意したときは誰かに預けようと必死になっている。ここに終活をどうすべきか問題が表れていると言えよう。自分が死んでも犬には幸せに暮らしてもらいたい。しかし、それは不可能だと分かったから、電車に飛び込んで心中しようとする。孤独な人間とはこういうものだということがよく分かる。
本作は犬の使い方が素晴らしい。特にラストシーンには大いに感銘を受けた。犬にも意思があって、長年連れ添った飼い主から離反する。ところが、それも僅かな間で、すぐさま和解に転じる。その様子がとてもチャーミングで救われた気分になった。
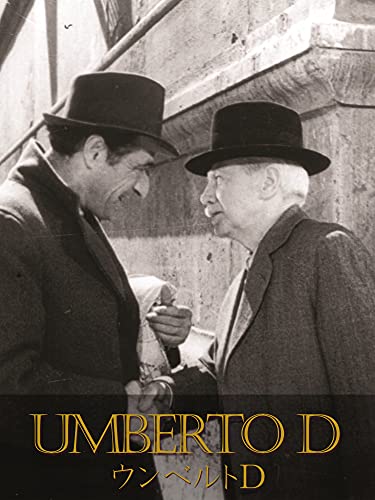



 巴里の屋根の下[HDレストア版](字幕版)](https://m.media-amazon.com/images/I/41tXB1ELlGL._SL500_.jpg)