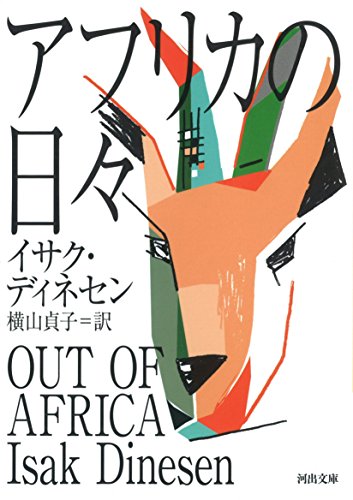★★★★★
イボ人のイフェメルはナイジェリアからアメリカに渡って13年が経っていた。帰郷する予定の彼女はヘアサロンで髪を結ってもらい、その最中に過去の出来事が語られていく。ラゴスで共に過ごしたオビンゼとの恋だったり、奨学金を得てアメリカに渡って大学に入るも仕事探しに苦労したり、新たな恋人とオバマ大統領の誕生を祝ったり。彼女は人種問題を題材にしたブロガーとして有名になっていた。
全米批評家協会賞受賞作。
これは素晴らしかった。アメリカ文学、あるいはアフリカ文学の枠組みに収まらない、広い意味での黒人文学の傑作といったところだろうか。本作を一言で要約するならば、「アメリカに渡って人種を発見し、帰ってきてラゴスを再発見する物語」であり、さらには人種問題という社会派要素とメロドラマという通俗性ががっちり噛み合っていて、分厚い本でありながらも、最後まで読ませる充実した内容になっている。教育を受けたナイジェリアのエリート層が母国でどのような生活を送り、アメリカやイギリスといった先進国でどのような苦労に直面するのか? 移民側の視点で描かれた本作は、各地で排外主義が横行する今こそ読まれるべきだと思う。
黒人にはアメリカ黒人と非アメリカ黒人(アメリカン・アフリカンとアフリカン・アメリカン)の2種類がいる、という指摘には目から鱗だった。前者はアメリカに住む奴隷を祖先に持つ黒人で、後者はアフリカから移民してきたエスニックな黒人。どちらもアメリカの最下層で謂れなき差別と苦労を強いられている。この小説は「髪の毛」が重要なモチーフになっていて、女性の場合、丹精に編み込んだ髪型が彼女たちのアイデンティティになっている。だから本作はヘアサロンの場面から始まっているのだけど、それにしても、黒人の髪型に詳しくないので具体的なイメージが著者近影の写真くらいしかなかった。ナイジェリアの黒人女性は皆、あんな素敵な髪型をしているのだろうか。ミシェル・オバマのストレートな髪型が黒人らしくない、という指摘には「へー」という感じだった。
V・S・ナイポール『暗い河』(1979)【Amazon】を巡るやりとりが印象に残っている。ある人物がこの小説を読んで、「現代アフリカのことが本当に理解できた」と述べるのだけど、それを聞いたイフェメルは鋭く反駁する。実は僕も『暗い河』を9年前に読んで感想を旧ブログに書いた。そして、アフリカを理解した気になっていた。あの小説には、第三世界の駄目っぷりとそこで暮らす個人の無力さが描かれていたのだ。『暗い河』は世間では名作とされているので、それに新たな光を当てたところは評価すべきだろう。
というわけで、世界を越境する黒人を描いた本作は、アメリカ文学としてもアフリカ文学としても新しいんじゃないかと思う。このまま行けば、著者は30年後くらいにノーベル文学賞を受賞しているだろう。これは推測でも願望でもなく予言である。チママンダ・ンゴズィ・アディーチェはノーベル文学賞を必ず獲る。