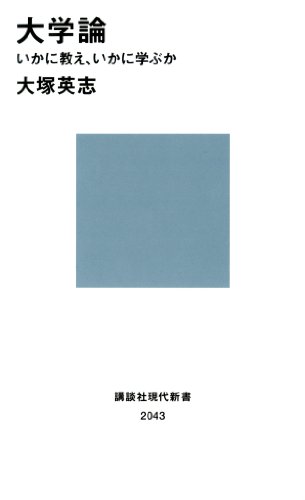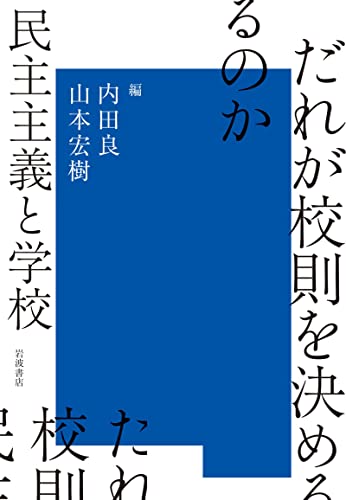2~3年前に書いた文章を読み返すと下手すぎてびびるのだが、これは成長した証なのだろう。しかし、いつになったら成長が止まって完成するのか。一生未完のまま終わるんじゃないかという不安がある。
2019年の本。ジャーナリストによる実録風のノンフィクションである。バブル崩壊からおよそ30年、その間に金融政策がどう推移していったか分かりやすく記述している。
金融破綻は高くつくから公的資金を注入してでも避けたい。しかし、それは国民が納得しないし、外国筋も「バッドバンクは潰せ」と圧力をかけてくる。90年代は難しい時代だった。
宮澤喜一と竹中平蔵が思いのほか優秀で先見の明があった。特に宮澤は1992年の段階で予防的な公金注入を目指していたが、様々な要因によって先延ばしになってしまう。そのツケは大きかった。
ペイオフを解禁するかどうかで議論があった。昔から抜くに抜けない伝家の宝刀だったが、危機にあって決断を迫られている。初めて適用されたのが日本振興銀行が破綻した2010年。国民に影響の少ない形で成された。この件に関しては先延ばしにして正解だったと思う。
失われた30年のデフレはなかなか厳しかったが、昨今のインフレはもっと厳しくて、経済の難しさを痛感している。
2010年の本。神戸の芸術大学で教えた経験から、以下のようなことを書いている。
このエッセイでは「まんがを教える大学」でぼくが彼ら彼女らに一体何をどのように「教え」、彼ら彼女らがどう「学び」、更にぼくが彼ら彼女らから何を「学び」、それはかつてぼくが大学で何をどのように「教わり」「学んだ」ことと連なっているのか、ということを書き連ねながら、「大学で教えること」と「大学で学ぶこと」という、ひどくありふれた、しかし、「大学に誰もが入れる時代」だからこそ改めて考えるべき問題について思いついたことを記していくことにする。(p.22)
三浦展のアンチテーゼであることは明白で、現場での経験を踏まえた地に足のついた内容になっている。風変わりな授業風景も去ることながら、自身の学生時代を現在の記述に織り交ぜ、教育について浮き彫りにしているところが特徴である。
戦後の漫画は映画に影響を受けている。石ノ森章太郎は『マンガ家入門』【Amazon】でそれを実践的に解説している。
石森は「まんが」を「映画らしく」見せるために、もしくは「まんが」を映画的に見せるためにコマの接合の論理にモンタージュ、そしてコマ内の構成にショット概念や空間の三分割に加えて、カメラワークという概念をかなり合理的に導入している。石森が進化させたのは旧『新宝島』の映画的手法なのである。無論、石森以前にもモンタージュとカメラワークを採用した先例はいくらでも見出だせるが、それを実作で洗練させた形で用いた上で入門書として解説してみせたという点で、石森のこの仕事の意味はまんが史の上でとても大きい。(p.88)
僕は小説を人並み以上に読んでいるし、映画も人並み以上に見ているが、漫画については人並み以下しか読んでないので、この指摘は目から鱗だった。今後漫画を読むときは映画を意識しながら読むことになるだろう。
教育風景は若者の青春群像みたいなところがあり、創作について葛藤が感じられるところが良かった。本書を読むと教育者とは「父」なのだと思う。自分が作ったカリキュラムを叩き込み、踏ん張りどころでは厳しく突き放す。獅子は我が子を千尋の谷に落とすのだ。大塚英志もまた江藤淳と同じ峻厳な教育者だった。それが興味深い。
A4版のムック。オールカラー。
ストレスに対して科学的なアプローチを取っており、人体に及ぼす影響からその対処法までしっかり書かれている。僕みたいな文系でも読みやすかった。
ストレスの長期化は全身の不調を引き起こす。皮膚の異常、呼吸器系の異常、肩こり、腰痛、頭痛。また、狭心症や心筋梗塞、糖尿病の発症率も上がる。過食症になったり味覚を失ったりもし、心因性の嘔吐も起こる。腹痛、下痢、便秘、胃潰瘍など消化器の症状のほか、めまい、耳鳴り、歯周病など多岐にわたる。
個人的にストレスは胃にくる。恋人と別れたときは3日間食事ができなかった。それ以前に緊張すると食が細くなるし、酷いときは吐き気もする。自分の胃の弱さが恨めしい。
1日あたり4000歩歩き、そのうちたった5分を早歩きにするだけで鬱病の予防が期待できる。青魚の摂取も精神疾患の予防にいいそうだ。
本読みとしては、読書によるストレス軽減効果の高さが目を引いた。1日6分読書することで、ストレスが68%軽減するのだという。これは散歩や音楽鑑賞、温かいお茶を飲むことより効果的で即効性が高い。また、読書をする人はしない人よりも平均寿命が2年長いという。読書は健康にいいようだ。
他にも色々書いてあるが、それは実際に読んでもらうということで。本書はストレスに悩まされている人にとって有益である。
2022年の本。校則に関する論文集である。執筆者は、内田良(名古屋大学教授)、山本宏樹(大東文化大学准教授)、松田洋介(大東文化大学教授)、鈴木雅博(明治大学准教授)、末富芳(日本大学教授)、福嶋尚子(千葉工業大学准教授)、西倉実季(東京理科大学准教授)、大津尚志(武庫川女子大学准教授)の8名。
校則の表記は反管理教育規範を元に曖昧にしているが、実際には厳格な管理教育を行っている。その事例が第3章のエナメルバッグ使用禁止のやりとりで明らかになっていて面白い。ザ・教育といった感じの理不尽さでのけぞってしまう。
規則とは必ずしも合理的に決められてない。だから保護者に説明する際は理由をひねり出す必要がある。そもそも校則は法律じゃないから従う義務なんてないのだが、それを曲げて従わせるのだから、外部を納得させる理由が必要なのだ。教師が世間知らずと目される所以は、ローカルルールを守るあまり世間の常識から外れるところにある。
現場は校則には明記されてない指導事項で満ち溢れている。しかし、だからと言って文書主義をとっているとゼロトレランスに向かってしまう。指導に関しては人間関係が重視されていて、必ずしも杓子定規に適用されているわけではない。こういった人治主義が緩衝材になっている点は注目に値する。
思うに中学生に「中学生らしさ」を要求するのは、女性に「女らしさ」を要求するのと同じくらい危ういのではないか。校則とは秩序の維持のために存在するが、必然的にそれは子供の人権とバッティングする。両者のバランスを取るのは難しい。
ところで、1月22日のこのニュースはタイムリーだった。
ネガティブ・ケイパビリティとは以下のような意味である。
ネガティブ・ケイパビリティ(negatetive capability 負の能力もしくは陰性能力)とは、「どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」をさします。
あるいは、「性急に証明や理由を求めずに、不確実さや不思議さ、懐疑の中にいることができる能力」を意味します。(p.3)
ポジティブ・ケイパビリティ(不確実な状況で素早く判断し、問題を解決する能力)では表層の問題のみを捉えて深層にある本当の問題を取り逃がしてしまう。だからネガティブ・ケイパビリティが重要なのだという。
本書自体が答えを性急に出さないネガティブ・ケイパビリティの実践となっているため、実用書として読むと肩透かしを食うだろう。一読したところ、山下清や『源氏物語』【Amazon】などの事例が事例として適切かどうか分からないし、ただ思いつくまま筆を走らせ水増ししたような印象さえある。読み終わった後も腑に落ちない。
ただ、ネガティブ・ケイパビリティという概念自体は重要で、学生時代から執拗に問題解決能力を要求された我々としては、立ち止まって考えるいい機会である。
ふと思ったが、プリキュアシリーズはネガティブ・ケイパビリティの実践ではないか。毎回目の前の小さな問題は解決するが、ラスボスという大きな問題は解決しない。1年かけてじっくり取り組んでいく。日本人はアニメを通じてこの概念を体得しているのだろう。
「頭がいい」という概念を脳科学の知見で多角的に検討している。
IQやEQ、記憶力のほか、「自分の身体を思い通りに動かす」ことも脳の機能として捉えているのが面白い。確かに一流のアスリートは頭がいいし、勉強が得意な人は総じて運動も得意である。
脳を正しく働かせるためには経験が重要らしい。それもただの経験ではなく、「能動的に」動くこと。試行錯誤を繰り返し、たくさん失敗する。そうやって予測と実測の差を縮めていく。「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」と言うが、僕は実際に経験したほうが理解度が高いと思っている。一度犯した失敗は魂に刻みつけられて一生忘れない。そこが他者の経験たる歴史との大きな違いだ。「歴史に学ぶ」とは最近流行りのタイパ志向で、映画を倍速で見るのと変わらないのかもしれない。
僕が考える「頭がいい」人はメタ認知能力が高い人だが、本書はその辺りに触れていなかった。これは脳科学ではなく心理学の問題なのだろう。
本書は章ごとに参考文献が挙げられているため、脳科学の入門書としてちょうどいい。
ダークな性格をマキャベリズム、サイコパシー、ナルシシズム、サディズムに分類し、心理学的な見地から説明していく。タイトルからは想像もつかない学術的な本だった。我々が日常会話で使う「性格が悪い」とは別次元の、より深度の深い記述がなされている。
本書で説明されている「性格」は学術的な意味でのパーソナリティで、紹介されている事例が「ダークな性格」では済まない人格障害のような印象だった。我々が日常会話で使う「性格が悪い」はもっと軽くてカジュアルなので、ここまでいくとちょっと違うかなと思う。
フィクションではサイコパシー的な特徴を持つ人物が魅力的に描かれている。シャーロック・ホームズがその代表例として挙げられているのが面白い。また、「ダークな性格の高さは、協調性の低さを基本的な特徴とする」という記述も納得がいく。確かに協調性の高いサイコパスなんて想像もつかない。
スパイトという概念が紹介されている。
スパイトとは、相手だけでなく自分自身にも危害を加えるような行為を指します。実際にその場で自分に危害が加わるような行為ではなくてもよいのですが、「こんな無茶なことをしたら自分の評判が下がってしまうかもしれない」と想像できるような行為とか「仕返しされても仕方がない」と開き直るような行為のように、自分にもネガティブな結果が生じることが明らかな行為も、ここには含まれます。(p.61)
要は社会的な自爆テロのことだが、SNSのインフルエンサーに多く見られるような気がする。フォロワーの多さと性格の悪さは比例するのかもしれない。
2024年11月の本。執筆時点で青葉真司は地裁で死刑判決を受け、控訴の意思を表明している。その後、2025年1月28日に控訴を取り下げて死刑が確定した(京アニ放火殺人事件 青葉真司被告の死刑確定 控訴取り下げで | 毎日新聞)。
オールドメディアらしい堅実な取材に基づいた本で、加害者・被害者双方から事件を照射したところが良かった。雨宮処凛や與那覇潤といった識者の分析も参考になる。
以下、印象に残った記述。
コンビニ強盗で実刑判決を受けた青葉被告は刑務所に。刑務所内で京アニ作品「けいおん!」を鑑賞。服役中もノートに小説のアイデアを書きためた。
出所する4カ月ほど前、刑務所のアンケートに書いている。
1年後の目標は「作家デビュー」。5年後に「家を買う」、10年後「大御所になる」。同じ頃、担当医に精神疾患と診断された。(pp.45-46)
貧困層が一発逆転を夢見て小説家を目指す。この発想は出版不況の現代においては頭が悪いとしか言いようがない。これならYouTuberを目指したほうがなんぼかマシだろう。持たざる者のキャリアプランとしては大いに間違っている。
第21回公判のやりとりも印象に残っている。
弁護人 「事件を起こす前に接してた人と、今接する人とでは、どう違うのか」
青葉被告 「親身になって対応していただき、愚痴を聞いたことがない。前は何事も自己責任だったが、何をやるにしても親身になって対応してもらっている」
弁護人 「青葉さんは裁判の前半で『底辺にいる人間』と言った。そういう環境とは違うか」
青葉被告 「底辺は、押し付け合い、押し付け合いの世界は、食い合いになっている世界で、(その中では)どう生き残るかしか考えていなかった。今は、献身以外の言葉がない。そういう人に対して、生き残りとか食い合いとか、考える必要性がない」(pp.90-91)
壮絶な生い立ちのうえ、家を出てからは仕事を転々とした青葉。関係者は「苦しいのはあなただけではない」と突き放すが、人生の苦しみなんてその人固有のものであり、他人が苦しかろうがそうでなかろうが自分の苦しみは1ミリたりとも軽減されない。「苦しいのはあなただけではない」という発言は、苦しみを乗り越える力を持った強者の論理だろう。青葉の生い立ちを読んだ後ではその言葉も虚しく響く。
青葉はロスジェネ世代であり、派遣の仕事を転々とした自身の境遇を、秋葉原事件を起こした加藤智大に重ねていた。一方、加藤は派遣労働が事件の動機ではないと否定したまま死刑に処されている。2人のコントラストが何とも言えない。
類書に津堅信之『京アニ事件』【Amazon】がある。2020年の本。京アニがどういう会社なのか掘り下げていて参考になる。
ところで、2019年に大阪芸術大学の教授が京アニを「麻薬の売人以下」と表現して炎上していた。
一人のおたくとして、僕はこの件を一生忘れないだろう。
また、1月31日に東洋経済オンラインが記事を出した。青葉についてよくまとまっている。
著者はバブル期に日経新聞の記者をしていた人。そのせいか、本書は経済学的な記述よりも群像劇風の人間ドラマのほうに重きを置いていた。とにかく人名がたくさん出てくる。特に直接会った人には思い入れが深いようだ。
当時を知る人の批評みたいな記述なので、歴史物語的な面白さがある。その反面、経済学的な記述は手薄なので、あまり勉強になった気はしない。これを読んだところでバブルの本質は掴めないが、「神は細部に宿る」との言葉通り、バブル期に活躍した人物に焦点を当てることで、時代の息遣いを感じ取れるようにはなっている。当時の逸話を読みたい人向けになるだろう。
個人的にはリクルート事件と尾上縫の記述が面白かった。
宮澤喜一と竹下登、2人の回顧録を突き合わせて戦後政治を浮き彫りにしている。思ったよりも批評的な本で、実在する人物について批評する行為のお手本になっている。
批評的というのは、たとえば宮澤についての以下の記述。
この満州の印象の中に、宮澤の物の認識の仕方の一つのプロトタイプ(原型)が出ているのではないでしょうか。今現にあるものは将来的には成功しないだろう、しかし今そこにある存在そのものについては、決して悪いものとはみなさない――つまり「それはそれなりに機能しているけれど、将来的にはうまくいかない」という感想です。
今見ている現場についてのある種のオプティミズムと、将来についてのシニシズムが同時に存在しているのです。これは宮澤という人を今後論じていくときの非常に重要なポイントであり、彼の物の見方の意外な深さを示していると思います。(pp.35-36)
また、竹下の実家は酒造業なのだが、酒の銘柄を変えたことについて以下のように書いている。
竹下家では、福本邦雄の父で「福本イズム」で知られる戦前の日本共産党幹部だった福本和夫との関係があったせいか、「日出正宗」という酒を「大衆」という名前に変えていたそうです。その「大衆」を、竹下が「出雲誉」という名前に変えたとここでは話しています。これは単に酒の銘柄を変えたということではなく、竹下家ないし竹下につながっている一つの思想のようなものを感じ取ることができます。一言でいえば、進歩的思想に理解は示すが、明らかな左旋回は避け、保守的な枠からはみでないようにすることです。(p.44)
いくら批評とはいえ、こんな大胆に飛躍していいのだろうか? 政治家としての人物像から逆算して解釈してないだろうか?
そんなわけで、細部に若干の疑問はあるものの、2人の政治家を通して戦後政治のうねりを体感できたのは良かった。
文体が過度にくだけていて読みづらいし、また、物事を『獅子の時代』(大昔のNHK大河ドラマ)の図式で説明していて分かりづらい。ただ、それらを除けば入門書としては悪くないのではないか。明治から始まる左翼の通史として基本的な知識は得られる。類書をあと2~3冊は読みたいところだ。
日本の左翼の出発点がキリスト教なのが面白い。
まずもって、日本最初の社会主義者たちが、こぞってキリスト教徒だったということに注意して下さい。内村鑑三が有名ですね。後に共産党の在外リーダーになる片山潜も、あとの説明で何度も出てくる山川均、大杉栄、荒畑寒村といった初期社会主義オールスターも、こぞって最初はキリスト教徒でした。
明治のこの時代、キリスト教は文明開化の象徴です。「進んだ西洋」にあこがれて、その価値観を取入れようとしたわけです。そして、その目から「遅れた日本」の世の中を見たら、多くの人々がそんな遅れた世の中のために犠牲になっている。これはなんとかしなければならないというのが出発点だったのだと思います。(p.38)
資本主義も社会主義(共産主義)も外国から来た双子の思想に過ぎず、両者の対立を含めての近代化なのだろう。
丸山眞男の「超国家主義の論理と心理」、「軍国支配者の精神形態」は今読んでもすごいらしい。僕の世代で丸山はいまいちピンとこないが、岩波書店から全15巻の『丸山眞男集』【Amazon】が出ているのは気になっている。
左翼の歴史が面白いのは敗北の歴史だからで、戦前も戦後も負けっぱなしなところに哀愁を感じる。
データをふんだんに用いた研究書。導かれる結論はすごく穏当で、読書に前のめりな自己啓発書のアンチテーゼになっている。
「遺伝と環境の相互作用」というのが読書にも働いていて、子供が本好きになるかどうかは遺伝が大きいようだ。つまり、遺伝が環境に影響するのである。
少し自分のことを語ると、僕の両親は本を読まない人間だったが、幼い僕には絵本の全集を買い与えてくれた。それを貪るように読んだのが僕の読書の原体験で、以後、おっさんになった現在まで本の虫になっている。一方、同じ環境で育った弟はまったく本を読まず、漫画やゲームを選好していた。遺伝と環境が似通っているのにこの違いは何だろう? 個人的に「遺伝と環境の相互作用」は眉唾だと思っている。
大学生の読書は二極化しており、ここ20年で不読率が高まった一方、1日1~2時間を読書に投じる読書家の割合も増えた。この結果をどう受け止めるべきか。読書は収入にも影響するので、経済格差が加速するのではと危惧している。
上中下巻。
映画『オッペンハイマー』の原作。原題は「American Prometheus」である。
2024年2月に「映像の世紀バタフライエフェクト マンハッタン計画」を見ていたので、ロスアラモスでの光景はイメージしやすかった。番組ではヴェルナー・ハイゼンベルクの存在感が強かったが、本書では二箇所にしか登場せず、ルイス・ストローズとの確執が軸になっている。
オッペンハイマーはマッカーシズムの犠牲者ではあるが、ハリウッド関係者に比べると悲壮感がない。弾劾された結果、返って国内外で名声を高めているのだ。それまでの「原爆の父」に加え、「ガリレオのように迫害された科学者」というイメージも得ている。元々金持ちだったから経済的に困ってないし、国外に移住することもなかった。生前に名誉回復(エンリコ・フェルミ賞の受賞)もなされている。
オッペンハイマーは共産党に入党したことはなかったが、若い頃はシンパのような立場だった。当時のインテリだったら仕方がないし、これで責められるのは理不尽だろう。アメリカは戦後も人種差別があったうえ、マッカーシズムによって大量の追放者を出した。こんな国はおよそ自由の国とは言えない。世界一の先進国とは思えないほど狂っている。
終盤にちょっと書かれているアインシュタインとのやりとりが印象的だった。さらに、若き日の毒リンゴ事件も強烈である。
以下はあってもなくてもどうでもいいパートだが、読書記録だけでは味気ないのでとりあえず公開しておく。
新年早々、以下のポストがバズっていた。
B'zなんて90年代はクソダサくて、文化的な素養が少しでもある人ならみんな大嫌いなのが当たり前だったことを忘れてはいけない。今はノスタルジーのおかげで変わったけど。これは大事なことです
— 齋藤 (@saito_d) 2024年12月31日
当時「文化的な素養」があった人はフリッパーズギターを聴いていた。2021年に小山田圭吾が炎上したのも偶然ではなく、90年代にB'zを腐していた層が逆にダサくなったことの証左である。今は一周回ってサブカルのほうがダサくなった。近年サブカルがおたくを叩いているのは自分たちのプライドを回復させるためで、その行為は猛烈にダサい。
ただ、小山田に関しては謝罪したせいでキャンセルされたのは気の毒で、沈黙を貫いていればああはならなかっただろう。SNS時代の我々は、炎上しても決して謝罪してはならないのだ。
豊崎由美のポストが炎上していた。
「芥川賞」で検索して、安堂ホセ氏への授賞に怒って「芥川賞なんてくだらない」みたいなことを投稿してる皆さん、安心して下さい、あなたがたは文学から選ばれてませんから。どうか、文学のない世界で頭の悪い愛国精神を発揮なさっていて下さい。
— 豊崎由美@とんちゃん (@toyozakishatyou) 2025年1月16日
あと批判する際は読んでから、ね……あ、読めないか。
豊崎自身も「文学から選ばれてない」ので審判できる立場ではないのだが、それにしてもこの裁断には宗教的なものが感じられて鼻白んでしまう。たとえば、「神から選ばれてない」と何が違うのか。文学を読んで驕り高ぶるのなら読む意味はないだろう。
とはいえ、文学が大衆に開かれているかと言えばそうでもなく、読むのに才能と訓練が必要なことも確かだ。豊崎の発言には問題があるが、一方で彼女を批判している連中にも肩入れできない。どうせ文学を読んでないだろうし。選民思想が理由で文学が滅ぶのなら別に滅んでもいいのではないか。
村上春樹についてのポスト。
またやってしまった。なかなかの上級日本語話者に「村上春樹好き?」って聞かれて「うーん、彼の性描写は男視点だからな。あのタイミングで自分の身体や行為を差し出す女はいないと思う」って本音を言ってしまった。でも、だってそうじゃない?
— 靴家さちこ (@Kutupon) 2025年1月18日
村上春樹ならバカにしてもいい、という風潮はどうかと思う。豊崎由美の言葉を借りれば「文学から選ばれてない」のだから。一方、ハルキストはキモいから遠慮なくバカにすべきで、あいつらは他人の小説を借りてナルシシズムを満たすオナニー猿である。村上は偉大なクリエイターだが、ハルキストは醜悪なクリーチャーだ。
人文系で勝つことについて。
人文系で勝つ方法って、三宅香帆、ゆる言語学ラジオ、COTEN、ゲンロンしかないの少し絶望的に思える。
— 蓮見スイ (@HasumiSuis) 2025年1月27日
人文知のマネタイズする手法が高度すぎて、正直後発でやっていくのがかなり苦しいように思える。
大学教授になって単著を出している人たちのほうが勝っていると思うが、要はアカデミズムから離れて勝つ方法だろうか。言い換えれば、インフルエンサーになる方法。そもそも人文系はパイが小さいので、労多くして功少なしという感じがする。働きながら趣味で創作や批評をすればいいのではないか。本業にしたらストレスで胃を悪くしそう。
その他、伊藤計劃と小松左京にまつわる怪文書が話題になったが、小さな村社会の出来事なので取り上げない。
今月読んで面白かった記事。
執筆者はおそらく川上量生だが、糸柳とドワンゴの話は涙なしでは読めない。
年末年始はNHKの番組をたくさん見た。
- BS1スペシャル「独占告白 渡辺恒雄~戦後政治はこうして作られた 昭和編」
- BS1スペシャル「独占告白 渡辺恒雄~戦後政治はこうして作られた 平成編」
- 映像の世紀バタフライエフェクト 太平洋戦争“言葉”で戦った男たち
- NHKスペシャル 量子もつれ アインシュタイン 最後の謎
- こころの時代 シリーズ徹底討論(7)「宗教と政治」宗教は「分断」をもたらすのか
- こころの時代 シリーズ徹底討論(8)「宗教と政治」「他者」とどう向き合うか
- 映像の世紀バタフライエフェクト 戦後日本の設計者 3人の宰相
- こころの時代 シリーズ徹底討論(9)「宗教と政治」「信教の自由」を問う
- クローズアップ現代『虎に翼』が描く“生きづらさ”の正体 脚本家・吉田恵里香
- NHKスペシャル 巻頭言2025 新・トランプ時代 混迷の世界はどこへ
- 朝までラーニング! 休養中の推しに 100分学んだ愛を叫ぶサンシャイン池崎
- 朝までラーニング! 10000分後、“時間の正体”を発表するエントロピー池崎。
- 100分de名著 100分de筒井康隆
- NHKスペシャル“冤(えん)罪”の深層~警視庁公安部・内部音声の衝撃~
- NHKスペシャル 新ジャポニズム 第1集MANGA わたしを解き放つ物語
どれも面白かった。やはりNHKの番組制作能力は日本一だ。民放を見なくなって久しいが(M-1も見ていない)、NHKはこれからも見続けるだろう。
プライム・ビデオで水樹奈々のライブ映像を見た。
思いのほか熱いステージで楽しめた。僕の老後はアニソンが演歌のポジションに取って代わっているに違いない。アニソンにあらずんばJ-POPにあらず、という空気ができつつある。
プライム・ビデオで水瀬いのりのライブ映像を見た。
声優のライブ映像を見たのはこれで3本目だが、本公演もパフォーマンスがすごくて感動した。往年のソロアイドルもこんな感じだったのだろうか。計算され尽くした身体表現に見入ってしまう。
ところで、ドヤコンガの件があったせいか、MCの中にドヤコンガの痕跡を見つけるようになってしまい、我ながらいかがなものかと思う。
プライム・ビデオで上坂すみれのライブ映像を見た。
めちゃくちゃアイドルしていてすごかった。箱が中規模で観客との距離が近いところがいい。そもそも上坂がおたく受けするキャラで、約束された勝利をもぎ取ってる感じである。キュートという言葉がこれほど似合う声優もいないだろう。電波ソングみたいな曲もまたすごい。
アニメタイムズ(プライム・ビデオの有料チャンネル)でi☆Risのライブ映像を見た。
実際に見に行くならこれくらいの箱がちょうどいい。演者との一体感が味わえる。
YouTubeで三宅香帆が批評の本を紹介している。
トップページのおすすめに出てきたのだが、最近の関心事をピンポイントで突いてきたので驚いている。Googleが恐ろしくなってきた。
三宅の本は読んだことがないが、江藤淳の影響下にあるようで気になっている。日本の批評界で今一番勢いがあるらしい(東浩紀ひとり勝ちの時代から三宅香帆ひとり勝ちの時代になったとか)。原稿仕事だけでなく、YouTuberもやっているところが今風である。年内に何か著作を読んでみたい。