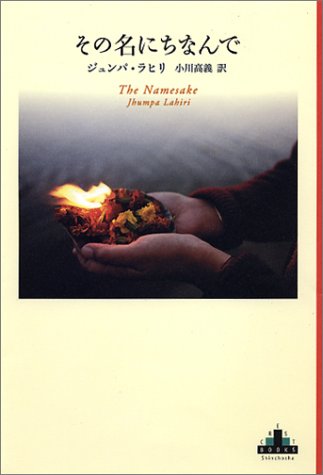★★★★
第二次世界大戦後のデンマーク。この国ではナチスが海岸線に200万以上の地雷を埋めたため、ドイツ人捕虜を使って除去作業をしていた。ラムスン軍曹(ローランド・ムーラー)が受け持つエリアにも9名の少年兵が割り当てられ、すべてを除去するまで故郷に帰さないと通達する。はじめは少年兵らを憎悪していた軍曹だったが、次第にその感情が和らいでいく。
デンマークって福祉国家のイメージがあるから、そこらの国よりは人権を重んじてるのだろうと思っていた。ところが、本作を観る限りではそうでもないみたい。彼らもまた侵略者に対して憎悪に燃えていた。捕虜のドイツ兵――それも少年兵――に地雷除去をさせるのって、国際法に照らしたら問題がありそうだけど、そういった倫理・道徳がすっ飛ばされるのだから厳しい。日本人の僕はシベリア抑留を連想したのだった。戦時中の仕返しとばかりに強制労働をさせるなんて、憎しみの連鎖をよく表している。戦争はスポーツと違って殺るか殺られるかの大勝負だ。勝ったほうが支配し、負けたほうが隷属する。先の大戦は枢軸国が悪いとはいえ、敗戦国とはつくづく惨めだと思う。
加害者をいかにして許すか? というのは大きな問題で、個人レベルでは可能でも集団レベルでは不可能ではないかと痛感している。ラムスン軍曹は少年兵らと触れ合うことで彼らに肩入れし、憎しみの感情を捨て去ることができた。しかし、軍曹の上官は現場にいないからそういう邂逅も果たせず、憎しみを保持したまま理不尽な命令を下している。加害者はあくまで加害者という態度なのだ。このような憎しみの連鎖を断ち切るには、対象と触れ合って相手を一人の人間、自分と同じ一人の人間として認めるしかないのだろう。しかし、それは容易なことではない。人間は感情で生きている動物であり、その感情を覆すには大きな体験を必要とする。そんな体験、誰もが得られるわけがない。ラムスン軍曹は運が良かっただけなのだ。この構造にやりきれなさを感じる。
本作では少年兵らが戦時中に何をしていたのかは明かされない。だから観ているほうとしても、彼らが一方的な被害者だと錯覚してしまう。故郷に帰りたがっている無垢な少年たち、といった具合に同情してしまう。しかし、彼らは戦時中に人を傷つけていたかもしれないし、もっと言えば人を殺していたかもしれない。そういった視点を持ち込んでもなお、相手に同情できるかがその人の試金石になるのだろう。願わくば、憎しみの連鎖はどこかで断ち切りたいものだ。