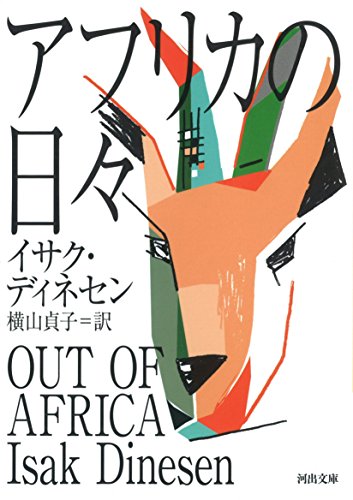★★★
部屋探しをしていた「ぼく」とフクスは、町外れの一軒家に間借りすべくその家に向かう。道中、2人は首くりりのスズメを発見するのだった。その後、宿泊先の部屋の天井に矢印があったため、その方向へ行くと、今度は首くくりの木切れを見つける。誰が何の意図でそんなことをしたのか?
「あんたはこのわしを、きっと、頭のおかしな男と思っとるだろうな?」
「いくらか」
「そういってもらうと楽だね。わしがちょっと気違いのふりをするのは、楽な気になるためさ。楽でもしなくちゃ、とてもやり切れやしないからね。あんたは楽しみが好きかね」
「好きです」
「官能のほうは? 好きかね」
「好きです」
「そうか、これでなんとか、お互いに意見が一致した。簡単な事さ。人間の……好きなものがある……何か? すすきっき。すきっきベルグ」(p.300)
本作はイスマイル・カダレ『誰がドルンチナを連れ戻したか』【Amazon】やアントニオ・タブッキ『ダマセーノ・モンテイロの失われた首』【Amazon】といった探偵小説仕立ての文学作品に分類できるだろう。ただし、作中に大きな謎はあるものの、それを明快に解く探偵はおらず、謎そのものは宙吊り状態のままで終わる。些細な日常に「徴」を見出して事件に関連づけていくところは、探偵小説のパロディと解釈できないこともない。すなわち、意味のないものに意味を嗅ぎ取るパラノイア的妄想だ。アントニイ・バークリーあたりがこういう小説を書いていてもおかしくなさそうだけど、不思議なことに書いてないのだった。
「ぼく」ことヴィトルドは、その場の勢いで家主一家の猫を絞め殺して庭の鉤に吊るしてしまう。まるで首くくりのスズメを模すように自ら新たな謎を作ってしまう。彼は探偵であると同時に犯人にもなるのだった。乱暴なことを言うと、探偵と犯人は探偵小説を構成する共犯であるわけだけど、ここまで露骨にその構造を再現してみせたのはなかなか面白い。左右の両端を結合することでその共犯関係を暴き出している。
最終章でルドヴィクの首吊り死体が発見されるところが衝撃的で、さらには何とも言えないユーモアを感じて笑ってしまった。イベントを通じてようやく「ぼく」の関連妄想が収まったと思ったら、ここに来て再燃してしまうのである。神の手(作者)のいたずらというか、よくここでスイッチを切り替えたものだと感心した。