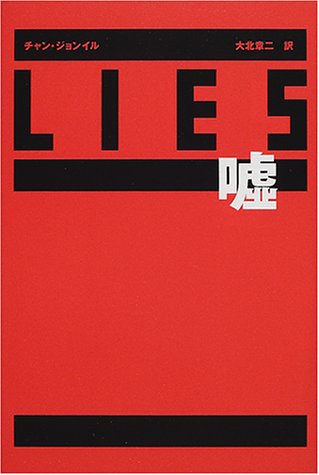★★★★
ナチス・ドイツ時代に法律家・保安部の役人・SS将校を勤め、戦後はフランスでレース工場の支配人になったマクシミリアン・アウエ。その彼が戦時中を回想する。法学博士にしてSS中尉の彼は、独ソ戦開始時のウクライナでユダヤ人虐殺の仕事に従事していた。始めは幕僚部で手伝い程度しかしていなかったが、後に自分でも1人ユダヤ人を殺すことになる。やがてヘマをしたアウエは、前線のあるスターリングラードに飛ばされるのだった。
(……)ロシア人にとってもわたしたちにとっても、人間はなんの値打ちもなく、〈民族〉、国家がすべてであり、その意味では、どちらも自分自身の像を互いに与え合っていた。ユダヤ人もまた、共同体、フォルクというこの強い感情を抱いていた。彼らは死者たちに涙し、可能であれば埋葬し、カディッシュを唱えたりする。しかし、たった一人が生き残っている限り、イスラエルは生きている。彼らがわたしたちの特権的な敵だったのは、おそらくこれが理由なのだ、つまり、彼らはあまりにわたしたちに似ていたのだ。(上 pp.107-8)
ゴンクール賞受賞作。
ボリュームたっぷりの力作だった。2段組みで900ページほどある。本作は1941年から45年までの出来事をSS将校の視点で描いていて、ナチス・ドイツが当時何をしていたのか、戦争がどのように推移していったのかを疑似体験できるところが良かった。こういうのはディテールがしっかりしたフィクションだからこそ味わえるもので、我ながら贅沢な楽しみだと思う。
本作を読んで強く感じたのは、人間は運に支配されているということだ。こうして僕がぬくぬくと平和を享受できているのは完全に運だし、また、ドイツ人としてユダヤ人を殺したり、ユダヤ人としてドイツ人に殺されたりするのも運で、その人がどういう立場になるのかは自分ではコントロールできない。どの時代のどの国に生まれたか、それは避け難い現実として我々の前に立ちはだかる。たとえば、ホロコーストを指揮したアイヒマンは、平時に生きていれば有能な官吏として地味に暮らしていただろうし、この時代のドイツに僕が生きていたら、それはもう恐ろしい出来事に関わっていたことだろう。人間は自分の人生を限られた幅でしか選択できない。そのことを強く実感したのだった。
語り手のアウエは叙事的に物事を語ることが多いので、彼がどういう考えでSS将校なんてやっているのかよく分からないところがあったけれど、時々自分の心情なり考察なりを述べることがあって、そういう部分がとても貴重に思えた。アウエはとにかく「立ち会う」ことが多い人物で、観察して何もしない立場を好んでいる。戦後から回想しているという形式のせいか、ナチスのイデオロギーを狂信的に信じているようには見えない。ただ、人と話すときはこちらもぎょっとするようなイデオロギー的な発言をしていて、本心がどこにあるのかいまいち掴めないところがある。そういう割り切れないところが人間の複雑さなのだろう。彼は同性愛や近親相姦といったタブーを平然と犯しているし、最後の最後に意外な行動をとっている。一筋縄ではいかない人物像だった。
強制収容所をめぐる問題で、政治的使命と経済的要求のどちらを優先させるか? という議論はとてもおぞましかった。イデオロギーに従ってユダヤ人を殺すか、それとも戦争に役立てるために生かして働かせるかという問題である。また、ボリシェヴィキとナチスの違いが、階級によってアプローチするか、人種によってアプローチするかの違いでしかないのも恐ろしく思えた。どちらの道も地獄しか待っていない。さらに、なぜユダヤ人を殺すのかという考察で、彼らがドイツ人と似ていて自分たちの中にあるその性質を殺すためというのは、随分と倒錯していると思った。ひとことで言えば、近親憎悪だろう。
これから絞首刑にするという女に対して、将校たちが次々とキスしていくエピソードが印象に残っている。それと、死んだ女の腹を帝王切開して赤ん坊を取り出すも、すぐに別の男がその赤ん坊を叩きつけて殺害するエピソードもすごい。戦時下における残酷な日常にぞっとした。