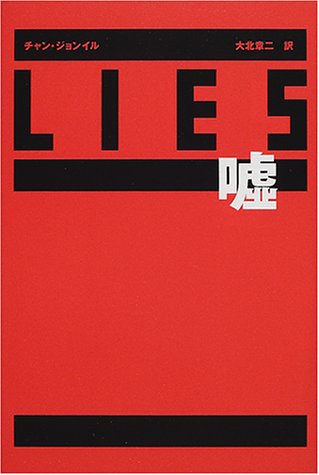★★★
江南の町・油坊鎮。庫東亮の父・庫文軒は、革命で犠牲になった女性烈士の息子として地元の指導者になっていた。ところが、調査によってその血筋が誤りであるとされ、庫文軒は階級の異分子として失脚する。彼はそれまで地位を笠に着て数多の女と不倫をしていた。庫父子は陸から離れて向陽船団に移り住む。やがて船団には慧仙という少女も加わるのだった。
ぼくはすわったまま、心に秘密を抱いていた。体が熱くなったり、冷たくこわばったりする。(……)ぼくは十三年間、父の監督を受けてきた。岸に上がったときだけ、レーダーのような父の厳しくて鋭い視線から逃れることができる。それは、いちばん自由なときだった。ぼくはその貴重な時間を使って、慧仙を監督している。いや、監督ではなく保護かもしれない。あるいは、保護ではなく監視かもしれない。どちらにしても、それは僕の権利ではない。ただ勝手に、こんな癖がついてしまったのだ。(p.258)
文化大革命の時代を扱っている割にはあまりそれっぽくなかった。確かに町の指導者(書記)から一晩にして立場が急落するところは文革っぽい。でも、この時代はもっと生死に関わることだらけで、たとえば紅衛兵に吊し上げを食らうのがお約束だと思っていた。大衆の前で自己批判させられたり、暴行されたりするあれ。しかし、本作にはそういうのがまったくなく、せいぜい町の自警団が幅を利かせる程度である。それと、この時代の中国では失脚したら逃げ場がないと思っていたけれど、陸上から水上に生活の拠点を移している人が多数いて意外に思った。水上の人たちは陸上の人たちに差別されているものの、命を脅かされるということはなく、一応は共存できている。ひとことで文革と言っても地域によって実情は違っていて、江南ではこんな感じだったのだろうか? ちょっと僕にはよく分からない。
語り手の庫東亮は陸上では「空屁」と馬鹿にされ、水上では父親から禁欲を課せられていて不憫だった。庫東亮は13歳から26歳までの間、父親に監視されながら生活している。父親は自分が性欲によって身を滅ぼしたから、その反動で息子には勃起も自慰も許さない。挙句の果てには、自分のペニスを半分に切断する暴挙に出ている。この親子関係がラストまで続く縦軸になっていて、ある種の苦味を伴いつつ、最後には意外な感興を呼び起こしている。また、本作では慧仙という少女も重要な役割を担っていて、彼女が河(水上)から岸(陸上)に生活の基盤を移そうと奮闘するところも見所だろう。庫東亮はそんな慧仙を長期にわたって監視し、一方的に思いを募らせるのだけど、それが最後に思わぬ形で返ってくるのも良かった。
それにしても、自分が女性烈士の血を引いていることに縋りつく父親の姿はとても悲しい。実際は根拠薄弱で、血を引いている可能性は限りなく低いというのに……。こういう人間的な弱さを描くところは魯迅の時代から変わっていないようだ。