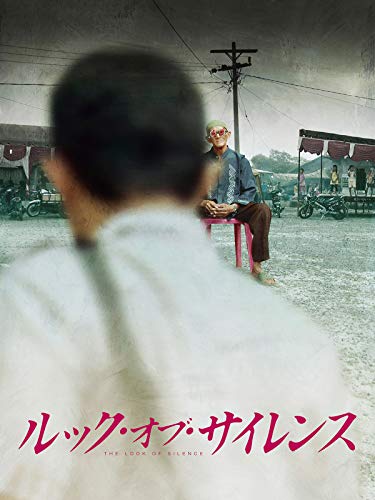★★★★
インドネシアでは、1965年のクーデター期に共産主義者とレッテルを貼られた人たちが100万人以上殺害された。眼鏡屋のアディは44歳。自分が生まれる前に兄を殺されている。ジョシュア・オッペンハイマーが持ってきたフィルムには、兄の殺害について得意げに語る2人の老人が映っており、アディは真剣な表情でそれを見る。アディは近所に住む加害者やその家族たちの元を訪れて対話する。
『アクト・オブ・キリング』の姉妹編。前作が加害者側からのアプローチなのに対し、本作は被害者側からアプローチしている。
被害者遺族のアディは様々な人のところへ話を聞きに行くのだけど、加害者たちは誰も反省してないし、謝罪の言葉もなくて暗澹たる気分になった。例によってみんな殺人を正当化している。ある老人は「過去は過去でしかない」と一蹴し、それどころかアディがプロパガンダのことを指摘すると、「政治的だ」と逆ギレしている。また、虐殺の司令官だった男は「自分にも上官がいた」と責任逃れをし、挙句の果てには自分が正しいとばかりに開き直っている。さらに、現役の議員は100万人が殺されたのを「それが政治だ」と語り、社会を良くするプロセスだったと説いている。遺族を目の前にしてもこの態度なのが恐ろしい。形だけの謝罪すらないのは、おそらく日本と違って謝ったら負けの文化なのだろう。だから心の底から後悔してないと謝罪できない。それゆえに、被害者が泣き寝入りする状況になっている。
一番ぞっとしたのは学校のシーンだ。教師が小学生くらいの子供たちに「共産主義者は悪だ」と教えている。これだけなら発展途上国にありがちな光景だけど、恐ろしいことに、教師が相手にしているのは共産主義者(とレッテルを貼られた人たち)の子孫なのだ。つまり、お前たちの先祖は悪だったと教えているのである。そのうえ、共産主義者の子孫は公務員になれない、お前たちは公務員になれない、とまで言い切っている。これを聞かされた子供たちはどう思ったことだろう? いい歳した大人が子供相手に何をしているのか? さらに、共産主義者は残酷だった、目をくり抜いた、将軍を殺した、とあからさまな嘘まで教えている。民主主義国家で暮らす我々は、何となく今のシステムが最良のものだと認識しているけれど、全然そんなことはないようだ。自分たちのイデオロギーを正当化するためなら、敵と目した人たちを迫害する。子供たちに嘘を教える。このシーンを観て、自分の拠り所にガツンと蹴りを入れられた気分になった。
アディの叔父はクーデター期に看守をやっていた。叔父は自分が虐殺の手助けをしたことについて、「国家を守るため」と述べている。これなんかは最低の言い訳ではなかろうか。せめて「自分を守るため」と言うべきだった。だいたい国家みたいなフィクションのために人殺しができるかよ。世の自称愛国者が信用できないのは、巨大な国家と卑小な自分を重ねているからで、その根拠はどこにあるのか不思議に思う。国家なんて集団生活を円滑に進めるためにただ便宜的に存在しているだけ。ただのシステムに過ぎないのだから、命を賭けるのは馬鹿げている。
というわけで、衝撃的なドキュメンタリー映画だった。