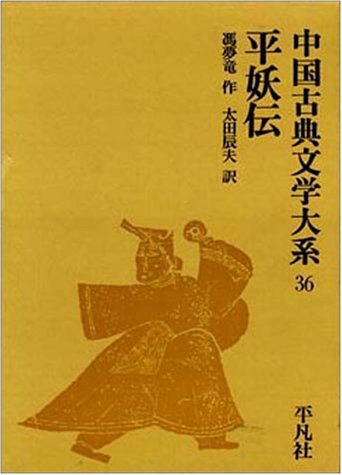★★★
1941年6月。戦闘機パイロットのトマス・プロッサーが、ドーヴァーの上空で太陽が2度昇るのを目撃する。そのことを本人から聞かされた17歳のジーン・サージャントは、空への憧れを募らせる。やがて警察官と結婚するジーン。20年の結婚生活を経てようやく妊娠するも、それを機に家を出るのだった。彼女は色々な場所を旅する。
「リンドバーグが大西洋を横断したときは」とレズリーが数フィート離れたところから解説した「サンドイッチを五つもっていったんだ。彼が食べたのはひとつと半分だけだったがね」
「あとはどうなったの?」
「あとのなにがだい?」
「あとの三つと半分よ」
レズリーおじさんは立ちあがったが、むっつりした顔をしていた。そこはフェアウェイではなかったけれど、たぶん彼女はしゃべってはいけなかったのだ。橅の実のあいだを、こんどはボールをさがしながら足をひきずって歩いていると、おじさんがとうとう、いらたただしげにつぶやいた「おそらく、サンドイッチ博物館にでも行ってるんだろうさ」(pp.18-19)
なぜミンクは生命力が強いのか? なぜリンドバーグは大西洋横断飛行のとき、サンドイッチを5つ持っていったのに、ひとつと半分しか食べなかったのか? どちらの問いも、現代だったらWikipediaかYahoo!知恵袋が答えてくれたかもしれない。この小説はジーンと彼女の息子グレゴリーが、世界と人生についての問いを抱きながら生きていくという内容だ。終盤では21世紀を舞台にしている。21世紀では対話型のコンピュータが問いに答えてくれるものの、人間とコンピュータは満足にコミュニケーションがとれない。質問の仕方がおかしい、みたいな指摘をしばしばされてしまう。この辺のSF要素は今読むといくぶん古さを感じるけれど、西洋人が人生についてどういう点を気にしているのか分かってなかなか興味深い。たとえば、神が存在するかどうか丹念に考察するところは西洋人らしいと言えるだろう。僕は存在しないんじゃないかと思っているけれど、そんなことはどうやっても証明することは出来ないし、永遠に謎のままだ。加えて、本作では自殺についても考察がされている。僕は社会が自殺を禁じている理由は、マクロ的には労働力や納税者が減ってしまうから、ミクロ的には家族や共同体に迷惑がかかるからだと思っている。神が禁じているからという宗教的な理由や、命は尊いからという人道的な理由は、どちらも後付けではないか。ともあれ、本当の質問とは訊かれた人間が既に答えを知っているような問いに限られている、という本作の定義は刺激的で、これは一種の哲学でさえあると思った。
登場人物で印象に残っているのは、レイチェルというレズビアンだ。彼女はレズビアンであると同時に、ミサンドリストでもあるのだった。実はTwitterではミソジニストとミサンドリストがバチバチ火花を散らしており、僕はその世界を垣間見たことがある。男がミソジニーになるのは女と関わらな過ぎるからで、女がミサンドリーになるのは男と関わり過ぎるから、というのが専ら言われていることだ。原理的には、ミソジニストは女が嫌いなのだからホモセクシャルでなければおかしいし、ミサンドリストは男が嫌いなのだからレズビアンでなければおかしい。僕はそう思っていたので、レイチェルがレズビアンにしてミサンドリストであることは、その説を裏付けられたような気がした。それと、男性全体、もしくは女性全体を憎むのって、ユダヤ人全体を憎んだナチス・ドイツにそっくりだと思う。いつかこれにまつわる犯罪が起きるのではないかと危惧している。