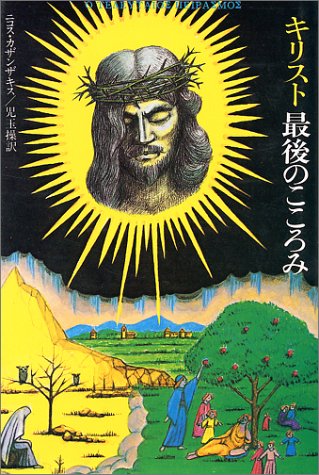★★★★
ニューヨーク。黒人の青年ファニーは、やってもいない強姦の罪で逮捕・収監されてしまう。ファニーの婚約者であるティッシュは、面会で彼の子を妊娠したことを告げる。ファニー、ティッシュの両家とも、ファニーを助けようと躍起になっていた。ティッシュの母は弁護士の指示で被害者のいるプエルトリコへ行く。
ファニーを救った情熱が、同時にファニーを災難に巻きこみ、牢屋行きの破目になった。ファニーは自分の中に自分自身の芯を見つけることができ、それが態度に現れたのだ。もう他人にへいこらする黒んぼなんかじゃない。この自由でございとうぬぼれているお国では、それは罪なんだ。誰かにへいこらする黒んぼでいなけりゃいけないんだ。誰にもへいこらしない黒んぼは悪い黒んぼなんだ。ファニーが下町に引っ越した時、警察もそう決めこんだのだった。(p.136)
人種差別を題材にした小説だけれども、書かれていることはプロテストだけに留まらず、家族愛や恋愛をもう一つの柱に据えていて、非常に生き生きとした内容の小説だった。20世紀後半のアメリカ文学はクオリティが高いと感心する。特に本作の場合は黒人の生活が興味深く、激しい人種差別に晒されながらも、みんなたくましく生きている。彼らは決して品行方正とは言えず、家族ぐるみで日常的に万引きや窃盗をしているのだけど、そういうのを包み隠さず描いていることがかえって好感が持てるというか、底辺ならではのリアリティがあって読ませる。ファニーがティッシュと初めてセックスした後、相手方の親に結婚の申し出をするエピソードなんか、読んでるこちらがドキドキしてしまうほどだった。
一番印象に残っているのは、ティッシュの妊娠を巡って、ファニーの家族とティッシュの家族で一悶着起きた場面。ティッシュが両家の人々がいる前で妊娠を報告したら、ファニーの母親が「あんたには悪霊が宿ってる」と言い出した。彼女はキリスト教の狂信者だったのだ。しかし、すぐさま彼女の夫が有無を言わさず妻を殴り倒していて、この場面は一種の喜劇と化している。協力すべき間柄がしょうもないことで揉めて、しかしさらにそれを乗り越えて協力する。生きるというのは、他者の他者性と否応なく向き合うことなのだと思う。
他者性と言えば、強姦の被害者とも結局は分かり合えず、彼女を説得できぬままティッシュの母はプエルトリコから帰国する。被害者は警察に誘導されるがまま、面通しでファニーを犯人だと断じるのだけど、それはもちろん冤罪で、真犯人は別にいるのだった。ただ色が黒いというだけで、ファニーを犯人と断じてしまう被害者。被害者はティッシュの母から理に適った説得を受けるも、最後まで自分の非を認めず、証言を翻そうとはしない。頑なにティッシュの母を拒否する。ここにも人間間の断絶があって、他者性というのは社会に偏在することを思い知らされた。
2018/11/27追記。2019年2月に『ビール・ストリートの恋人たち』という邦題で映画が公開されるとのこと。監督はバリー・ジェンキンス。
2018/12/01追記。映画公開に合わせて早川書房から新訳『ビール・ストリートの恋人たち』が出版された。翻訳は川副智子。